医薬品等の個人輸入について
1.医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証を取得していただくことになりました。
- 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、海外で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。
- 一般の個人が輸入(いわゆる個人輸入)することができるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した製品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
- 個人輸入には、原則として地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がある。
- 一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。
| 医薬品又は医薬部外品 |
●上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内 |
|---|---|
| 化粧品 |
基本的に、医薬品の場合と同じく、個人的に使用する場合に限り、一般の個人による輸入が認められます。 ●標準サイズで1品目24個以内
|
| 医療機器 |
(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法
注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します。 1.の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。 3.の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。 上記の範囲を超えた個人輸入の場合、輸入確認の申請が必要となります。申請方法、発給要件については下記リンク先を参照願います。
※輸入確認証を取得せずに、個人輸入が可能な数量に対応する期間(毒薬、劇薬又は処方箋医薬品の場合は1か月間、毒薬、劇薬又は処方箋医薬品に該当しない内用医薬品・医薬部外品の場合は2か月間、使い捨て医療機器(生理用タンポン、1日使い捨て又は一定の使用期間が設定されたコンタクトレンズなど)の場合は2か月間等) |
| 再生医療等製品 | 用法・用量・使用方法からみて1ヶ月分以内のもの |
- 医師の処方箋又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とするもの)については一般の個人による輸入は認められません。
- 脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分(海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して個人輸入する場合を除き、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品等)については、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いことから、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除きます。)。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
2.輸入が規制されている薬物等
| 麻薬及び向精神薬、 医薬品覚醒剤原料 |
麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。 (本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)
|
|---|---|
| 覚醒剤 | 「覚醒剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。 |
| 大麻 | 「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。 |
| 指定薬物 | 亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、医薬品医療機器等法第2条第15項の規定に基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。 |
| その他 |
|
3.医薬品等輸入確認情報システム
「医薬品等輸入確認情報システム」とは個人が自ら使用するために医薬品等を輸入する場合、又は医師等が自己の患者の治療や診断に使用する医薬品等を輸入する場合に必要となる輸入確認証の手続きをオンラインで行えるようにするものです。
令和5年2月1日から「医薬品等輸入確認情報システム」の運用が開始され、オンラインでの手続きが可能となりました。
オンライン申請が可能な申請区分は、以下の3つです。
- 個人使用のために輸入する場合
- 医師等が治療に用いるために輸入する場合
- 試験研究等を目的に輸入する場合
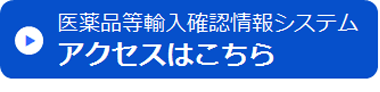
4.お問い合わせ先
- 輸入確認の申請先
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の個人輸入に関しては、貨物が輸入される区域を管轄する税関に応じて、担当する下記の地方厚生局(薬事監視指導課)にお尋ねください。
〇関東信越厚生局(函館税関、東京税関又は横浜税関)
電話 : 048-740-0800 FAX : 048-601-1336
〇近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関)
電話 : 06-6942-4096 FAX : 06-6942-2472 - 麻薬、向精神薬、覚せい剤、指定薬物等に関しては、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課麻薬係にFAXにてお問い合わせください。
FAX : 03-3501-0034 - 「ワシントン条約」に関しては、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課にお問い合わせください。電話 : 03-3501-1659
経済産業省ホームページ(ワシントン条約関係) - 「知的財産侵害物品」に関しては、東京税関業務部総括知的財産調査官にお問い合わせください。
電話 : 03-3599-6369
税関ホームページ(知的財産侵害物品の取締)
参考リンク
- 啓発パンフレット:「健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方へ」
- 啓発パンフレット:「医師・歯科医師による医薬品等の個人輸入について」
- 医薬品等の個人輸入に関するQ&A
- 医薬品等の輸入手続きについて(関東信越厚生局)
- パンフレット「個人輸入通関手続きの案内」(税関)※通関手続や関税の解説を紹介しています
■渡航先への医薬品携帯について■
海外渡航先への医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて、自己の疾病の治療に用いる場合であっても、医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)を所持して海外に渡航する場合には、渡航先の国によって、医師の診断書などの書類を携帯したり、持ち込んだり持ち出したりすることができる数量に制限があったり、事前に許可申請をする必要があることがあります。
本ホームページでは、各国の制度について調査し、結果が整ったものから順次掲載しています。
医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)を所持して海外に渡航する場合には、下記の共通事項にも十分留意した上で、各国の制度に従って必要な準備や手続きを行いましょう。
<共通事項>
1.どのような医薬品を服用しているのか、どのような病気・症状によりその医薬品を服用しているのか、説明できる文書を準備しましょう。
- 海外に医薬品を持参する時には、海外において、自分がどのような医薬品をどのような病気・症状で服用しているのかを説明できる文書を携帯することが望まれます。
- 渡航先の国によっては、特定の文書の提示を求められること(例えば、英文による医師の診断書など)がありますので、事前に確認して準備することが必要です。
2.医薬品は、本来の容器に入れたまま持参しましょう。
- 海外に医薬品を持参する時には、医薬品を本来の容器のまま(例えば、PTP包装入りの錠剤やカプセル剤の場合にはそのまま、瓶入りの医薬品の場合には病院や薬局で交付された瓶入りのまま)で持参しましょう。
- 他の容器に移し替えると、どのような医薬品なのか確認することが難しくなり、渡航先の国によっては持ち込めないことがあります。
- 複数の錠剤などを一度に服用する必要があって、一度に服用する分をPTPシートなどから取り出して一包みにしている場合(「一包化」と言います。)は、事前に薬剤師に相談しましょう。
- 粉薬は、海外では違法薬物の疑いを掛けられるおそれがあるので、そのような医薬品を服用している場合には、他の剤形の医薬品に変更できないか、事前に医師や薬剤師に相談しましょう。
3.医薬品は、渡航中に必要と考えられる分を超えて持参することは避けましょう。
- 医薬品は、渡航中に必要と考えられる分を超えて持参することは避けましょう。
- 必要以上に多量の医薬品は、渡航先の国によっては、持ち込みが認められないおそれがあります。
- 渡航先の国によっては、滞在期間にかかわらず、一度に持参できる医薬品の数量に上限がある場合があるので、事前に確認することが重要です。
4.医薬品を渡航者が自ら持ち込まずに、別に郵送したりすることは避けましょう。
- 医薬品を渡航先の国に持ち込む場合には、その医薬品を使用する渡航者が自ら持ち込みましょう。
- 渡航先の国によっては、郵送による医薬品の持ち込みを一切認めていないところがあります。
- 渡航先の国において医薬品が不足した場合には、安易に日本にあるものを渡航先の国に郵送するよう依頼するのではなく、まず、渡航先の国のルールがどのようになっているか確認することが必要です。
5.事前に、渡航先の国の情報を十分に確認しましょう。
- 渡航先の国によっては、その国の医薬品の持ち込み・持ち出しのルールをインターネット上で説明している場合があります。このような情報を入手して、必要な手続きを確認しましょう。
- 旅行会社を利用して旅行する場合には、旅行会社に渡航先の国に医薬品の持ち込み・持ち出しが可能か、事前に相談しましょう。
6.医薬品によっては、日本から出国で持ち出すことや、日本に帰国で持ち込むことにも事前に手続きが必要な場合があります。
- 医療用麻薬は、医師から処方を受けた本人が自己の疾病の治療の目的で、日本から出国時に携帯して持ち出すこと、日本に帰国時に携帯して持ち込むことのそれぞれについて、事前に厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に申請して、許可を得る必要があります。医療用麻薬を郵送で持ち出し・持ち込みしたり、他人用の医療用麻薬を持ち込み・持ち出しすることはできません。(許可の申請方法などは、下記のURLを参照してください。)
- 医療用向精神薬は、医師から処方を受けた本人が自己の疾病の治療の目的で、日本から出国時に携帯して持ち出すこと、日本に帰国時に携帯して持ち込むことができます。ただし、「1ヶ月分を超える分量」又は「注射剤である医療用の向精神薬」を携帯して日本に持ち込む場合は、医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類を携行する必要があります。(詳細は、下記のURLを参照してください。)
(参考)
厚生労働省麻薬取締部ホームページ「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」
https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html
<各国の制度>
アジア
大洋州
欧州
北米
中東
アフリカ
■個人輸入代行業の指導・取締り等について■
1.いわゆる「輸入代行」による トラブルが増えています。
個人輸入代行と称し、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。 日本の医薬品医療機器等法に基づく承認等を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは違法な行為です。
また、トラブルが生じた場合、輸入代行業者は責任を負わず購入者の責任とされることがあります。
インターネットを利用する際には、業者の氏名、名称、 住所、電話番号がサイトに掲載されているか、また、個人輸入できる医薬品等であるか情報を事前にご確認ください。
2.輸入代行業者を利用する際には、くれぐれもご注意ください。
- 輸入代行業者の行う業務の範囲については、一般に、輸入者の要請に基づき個別商品の輸入に関する役務(手続き)を請け負うものであり、商品の受け取り等の輸入の効果が帰属する場合は、輸入販売業の許可の取得が必要である。
- 輸入代行業者が、無承認医薬品である商品のリストを不特定多数の者に示し、その輸入の希望を募ることは、商品リストが無承認医薬品の広告に該当し医薬品医療機器等法違反となる。 なお、商品名が伏せ字などであっても、当該商品の認知度、付随している写真等から総合的にみて広告に該当すると考えられる場合は、医薬品医療機器等法違反となる。
- 輸入代行業者が、予め注文を見込んで個人使用目的として輸入していた商品を消費者に渡す、又は消費者の依頼に応じて自らの資金で商品を輸入し消費者に渡す。これらは、輸入販売業の許可が必要となるため、許可なく行えば医薬品医療機器等法違反となる。
<違反とならないケース>
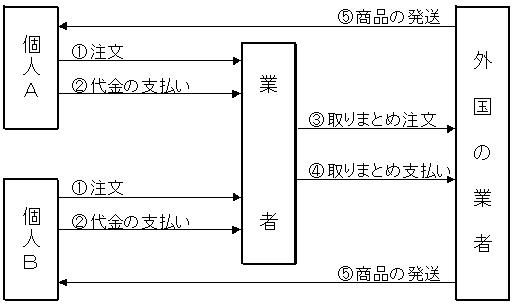
- 個人A,Bは輸入代行業者に希望する商品の輸入を依頼する。
- 個人A,Bは輸入代行業者の手数料が上乗せされた価格を支払う。
- 輸入代行業者は、預かった代金等をとりまとめ、送付先等リスト(消費者の氏名、現住所等)とともに、外国の販売業者に送付する。
- 外国の販売業者は、消費者に対し、直接商品を送付する。(個人A,B=輸入者)
- 詳しくは、こちら「個人輸入代行業の指導・取締り等について」をご覧ください。
出典元:厚生労働省